
お正月になると大人から子どもに渡すお年玉。
子どもの頃はお正月の1つの醍醐味としてとても楽しみにしていた方も多かったと思いますが、大人になってお年玉をあげる立場になると少し気が重いですよね。
実はこのお年玉袋(ポチ袋)、名前の書き方やお札の入れ方などにマナーがあることをご存じですか?
知らないと気まずい思いをしてしまうかも。
そこで今回はなぜお正月にお年玉を渡すのか、ポチ袋の名前の由来やポチ袋の表と裏の名前の書き方お札の折り方や入れ方など、意外と知らないマナーなどをご紹介していきます。
スポンサードリンク
目次 [表示]
お年玉とは
まずは「お年玉とは何か?」について軽く触れておきたいと思います。
お年玉とは「新年のお祝いとして子どもや使用人に贈る金品のこと」。
現在では、「大人から子どもに金銭を与える習慣及びその金銭のこと」を指します。
お歳暮などと違って目上の人が目下の人に贈るのがお年玉の特徴と言えますね。
お正月に子どもにお年玉を渡す由来
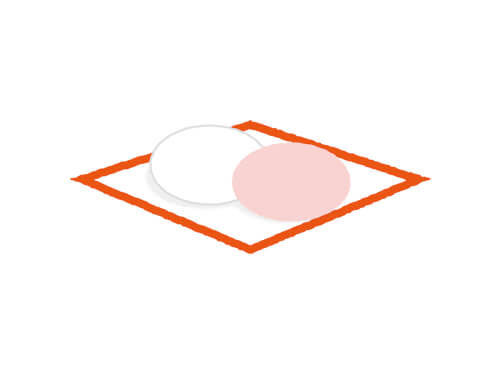
現在では、大人から子どもにお年玉を渡すのがお正月の恒例行事の1つでもありますよね。
では、なぜお正月に大人は子どもにお年玉を渡すようになったのでしょうか?
その由来について見ていきましょう。
そもそも昔のお正月とは「年神様」を家にお迎えしたおもてなしすることを目的としていて、「新しい年の幸福や恵を願い、魂を頂く」という意味でもあります。
その中で”鏡餅”は年神様の依り代(家にいらした年神様の魂が鏡餅に宿ること)で、その鏡餅の餅玉が年神様の魂であり、その年の「年魂(としだま)」とされていました。
その餅玉を食べることでその年の魂を頂く(年を重ねることができる)と考えられていて、ちなみにですがその餅玉を食べる時の料理がお雑煮なんですよ。
その為、お正月に家長が家族にその餅玉を「御年魂」「御年玉」として与えていたことが由来だと言われています。
その後、少しずつ変化していき「目上の人」から「「目下の人」に金品を与えるようになり、現在は大人が子どもにお金を渡す「お年玉」になったそうです。
なので、目下の人、例えば部下が上司の子どもにお年玉をあげたりするのは失礼になるんです。
意外と知られていない大人が子どもにお年玉を渡す由来。
ぜひ覚えておいてくださいね。
ポチ袋の名前の由来

続いてはポチ袋の名前の由来について解説します。
ポチ袋の発祥は関西で、その関西の方言で「心づけ、祝儀」という意味で舞妓さんに与えられる祝儀袋の意味として使われていました。
「これっぽっち(少ない、小さな)」という言葉があり、少ないですが…という謙虚な気持ちで渡したのが始まり。
これがお正月にお年玉を渡す時の定番となっていったようです。
子どもからするとお金をもらえるということが嬉しいことなので、あまり意味は気にならないと思いますが、知っていればおもしろいですね。
ちなみに、「お年玉をいくら上げたら良いのか分からない」という人は下記の記事を参考にしてみてください。
お年玉袋(ポチ袋)の名前の書き方
それでは続いてお年玉袋(ポチ袋)の名前の書き方についてです。
あまり書き方について深く考えたことはないかもしれませんが、きちんとした書き方があるので今後の参考にしてみてくださいね。
簡単なことではありますが、年齢が小さい子どもに対してあげるお年玉の場合は、「〜ちゃんへ」「〜くんへ」という風に子どもが読めるようにひらがなで名前を書きます。
漢字でもいいのですが、子どもが自分の名前をすんなりと読めると嬉しく感られるので、ひらがなで名前を書く書き方が1番いいでしょう。
また、ある程度の年齢に達した子どもにお年玉をあげる場合は、「〜さんへ」と名前を書くのがベストです。
お年玉をあげる子どもは親戚や可愛がっている子どもなので、「〜ちゃんへ」などと書きたくなるかもしれませんが、少し子供染みた書き方なので、変えた方がいいと思いますよ。
今年のお正月からはこれらを参考にして変えてみてくださいね。
お年玉袋の表と裏の書き方
先ほどはお年玉袋(ポチ袋)の名前の書き方をご紹介しましたが、その名前はどこに書くか知っていますか?
間違えた書き方をしているかもしれないので、しっかりと身につけておきましょう。
結婚式などのご祝儀袋では、表面に自分の名前を書きますが、お年玉袋(ポチ袋)の場合は正反対で裏面に自分の名前を書きます。
その時、子どもから見て分かりやすい「おじいちゃんより」「おばさんより」などという書き方をしてあげるのがいいでしょう。
表面には当然、お年玉をあげる子どもの名前を書きます。
先ほど紹介したような「〜くんへ」などと書いてくださいね。
もし、表面に書くスペースがないときは、裏面に「金伍千円」など金額を記入して名前と区別しておくのが良いです。
間違った書き方をしていた方は、今年から直してくださいね。
スポンサードリンク
お札の折り方や入れ方
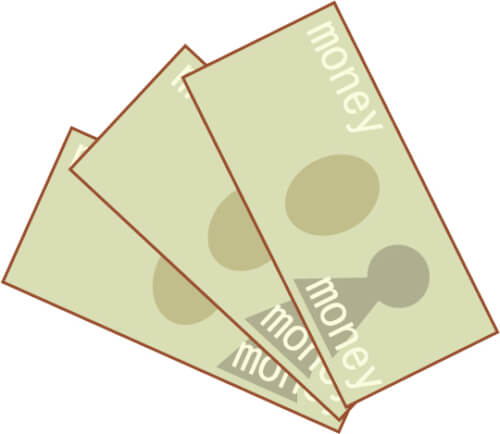
お札の折り方や入れ方にも実はマナーがあります。
お札の折り方は「三つ折り」が1番キレイな折り方とされています。
間違えた折り方をしていた方は、次から三つ折り方に変えてくださいね。
思っている以上にキレイに収まるので、気持ちがいいですよ。
また、ただ単に三つ折りに折るのではなく、お札の肖像が内側になるように左、右の順で折る折り方がキレイなのでそのようにしてみてください。
そしてお札の入れ方ですが、お札の天地が逆にならないように気をつけて入れます。
せっかくキレイに折ったのに逆に入れてしまっては元も子もありません。
入れ方に関しては1つしか注意点はありませんが、その1つに気をつけてくださいね。
お年玉袋(ポチ袋)に入れるお札は折ってしまいますが、なるべく新札にしましょう。
お札の折り方や入れ方にまでマナーがあったなんて驚きですよね。
無意識のうちにきちんとした折り方や入れ方ができていたなんてこともありますが、できていなかった人は今度からお札の折り方や入れ方を直していきましょう。
まとめ
今回はお正月にお年玉を大人が子どもに渡す由来やポチ袋の名前の書き方、お札の折り方や入れ方についてもご紹介してきましたが、意外と知らないことが多かったのではないでしょうか。
知っておかないと恥とまではいきませんが、常識の1つとして頭に置いておいてくださいね。
1人でも多くの方が素敵なお正月を過ごせますように!
スポンサードリンク











