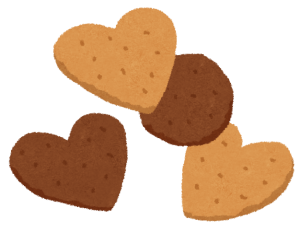ライム、カボス、スダチ・・・この3つの区別、つきますか?
「あ、知ってる! 秋刀魚に添えてある、あの柑橘類でしょう?」
確かにそうなのですが、例えば野菜売り場でカボスとスダチが並んでいた時、さらにその横にライムまで並んでいたら、その見分け方わかりますか?
ライム、カボス、スダチは3つともミカン科の柑橘類で同じ色という共通点はありますが、よく確認してみるとその特徴はわかりやすく味や使い方も違うので、実は見分け方はとても簡単なのです。
それでは、この3つの違いと見分け方をまとめてご紹介します。




スポンサードリンク
目次 [表示]
ライムの特徴


ライムは、インド、ミャンマー、マレーシア一帯の熱帯地域が原産と言われている低木の柑橘類の実で、現在はカリフォルニアやメキシコで多く栽培されています。
日本で流通しているライムはほとんどが海外から輸入されたものですが、日本でも少しですが愛媛や香川で栽培されているそうです。
カボスやスダチレモンと比べると、あまり日本では流通していないような感じがしますね。
違いと見分け方
実の形はレモンととてもよく似ていますが、色は緑色でレモンよりもよりも小ぶりなのが特徴です。
また、カボスやスダチと形を比べると、ライムはレモンのようなラグビーボールのような形をしているのが大きな特徴、見分け方が簡単ですね。
味の違いと用途


「香酸柑橘類(こうさんかんきつるい)」と言われているライム、酸味や香りが強くて生食にはあまり向きません。
ライムはレモンと形が似ていますし、味が似ていて酸っぱいのですが、レモンよりも苦みも強いのが特徴。
この苦みは、ライムに含まれる「葉酸」や「カリウム」のせい。
このライムは、しぼり汁をジュースやカクテルにしたり、また、香りが良いので実をスライスしたりくし形に切ったりして料理に添えて使います。
カクテルの中でも有名な「ジントニック」や「ジンライム」、「モスコミュール」の中にはライムのしぼり汁を使っているものもあるのだとか。
「レモンとよく似てるし、お菓子やお料理にも使えるの?」
使えないことはありませんが、ライムはレモンよりも苦みが強いのでお料理やお菓子作りには向かないかもしれませんね。
カボスの特徴


カボスは大分県原産の柑橘類で、熟すとゆずのように黄色になりますが、緑色のうちに収穫してしまいます。
大分県では、昔から民家や農家の庭先にカボスを植えて薬用として使っていたそうです。
江戸時代、宗源という医者が京都から大分にカボスの苗を持って帰ったことが、大分県でカボスが栽培されたきっかけと伝えられていて、大分県臼杵(うすき)市内には、今も樹齢200年程のカボスの木が残っているのです。
大分県以外で、これほど古いカボスの木が残っていないことから、カボスの原産地は大分県、と言われているそうですよ。
違いと見分け方
1個の大きさが100g~150g程で大体テニスボール位の大きさ。
雌花跡がある実の上の部分がドーナツ型をしていて少し盛り上がり気味なところが特徴です。
スダチやライムと並べると、スダチよりも大きく、ライムのようなラグビーボール型をしていないのが違いですね。
味の違いと用途


カボスも「香酸柑橘類」と言われていて、酸味が強くて生食には向いていません。
味わいは酸味が弱くまろやかなのが特徴、素材の味わいと相性が良い事から、焼き魚や鶏肉料理にかけて食べることが多いです。
お刺身の醤油や、天ぷらのつけ汁にカボスの汁を入れていただくと、風味良くさっぱりと頂くことが出来ます。
また、ミネラル分が豊富で塩味もしっかりしているので、料理の時に塩の代わりにカボスの汁を入れることもあるのだとか。
他にもポン酢にしてみたり、またジュースにすることもあるそうです。
スポンサードリンク
スダチの特徴


スダチは、徳島県原産の柑橘類です。
「スダチ」という名前の由来は、このスダチの絞り汁がお酢として使われていたことがあり、「酢の橘」という別名があり、それが「スダチ」という名前になったのだとか。
熟すとカボスと同じように黄色くなりますが熟す前に収穫されますので、私たちがスーパーでよく見かけるカボスは熟す前の緑色の果実です。
また、スダチの生産量は徳島県が一番多く国内で流通しているスダチの98%が徳島産のスダチで、スダチの花は徳島県の県の花に指定されているほど、徳島県にとってはなじみの深いものなのですね。
違いと見分け方
スダチの大きさは大体1個40g程でとても小さいです。
カボスと並べると違いも分かりやすく、小さいのがスダチ、大きいのがカボス、という見分け方が出来ます。
またライムと並べるとさらに違いが判りやすく、ライムよりも小さく形が丸みを帯びているのが特徴ですね。
味の特徴と用途


スダチもまた、ライムやカボスと同じく「香酸柑橘類」と言われていて、生食には向きません。
カボスと比べて酸味がはっきりしているのが大きな特徴で、白身魚やイカ、エビなどのお刺身に醤油をかけずにスダチをかけるだけでも風味と酸味が効いて美味しくいただくことが出来ます。
また、お料理だけではなくジュースにして飲むことも。
徳島の方では毎日何らかの料理でスダチを使っているのだそうです。
秋刀魚に添える柑橘類は?


さて、冒頭でも少し触れましたが、秋の味覚、「秋刀魚」を食べるとき、大根おろしに醤油と柑橘類を絞って食べるのが一般的だと思うのですが、あの秋刀魚に添えられている「緑色の皮の柑橘類」は何だと思いますか?
なんとなく「スダチかな?」と私は思っていたのですが、実は秋刀魚や焼き魚に添える柑橘類、なかなか地方性があって面白いのです。
秋刀魚や焼き魚に柑橘類を添える習慣は、東北地方ではほとんど見られず、関東地方近辺では添える人、添えない人様々。
一方、西日本は「秋刀魚には柑橘類だろう!」と言われるほど、当たり前のように柑橘類を添えるそうです。
そして、添える柑橘類も地域によって違って、徳島県とその近辺の県では「スダチ」をかけるのが一般的なのですが、大分県や宮崎県では「カボス」をかけて食べるのだとか。
さすがに「ライム」をかけて食べる人はあまりいないそうなのですが、沖縄では「シークワーサ」をかけて食べるところもあるそうで、産地の影響を強く表しているようです。
「レモン」をかけるのが一般的だと思っていた方にとっては、もしかしたら驚きの事実かもしれませんね。
まとめ
ライムとカボス、スダチの違いと見分け方をまとめてみましたがいかがでしたか?
・レモンとよく似た形でレモンより少し小ぶり、味は酸味と苦みがあるのがライム
・テニスボール位の大きさで、酸味が穏やかなのがカボス
・実が小ぶりで酸味が強く、醤油の代わりにお刺身にかけて食べられるのがスダチ
思ったよりも特徴が判りやすかったですね。
それぞれの食べ方も少しずつ違いますが、、好みや地域性もあるので「これが定番!」というのはなかなか見つけにくく、食べ方から違いを探るのは難しかったのですが、どれも「生食はせず、食材に添えたりかけたりするのが美味しい」ようですね。
機会がありましたら、それぞれを実際に食べてみて、特徴を味わってみるのも面白いですよ。
スポンサードリンク